ピークパフォーマンスカレッジ

得られるスキル/講義内容
パフォーマンスアップ / 発揮の階層構造に沿ったスキル学習
選手のパフォーマンスアップと発揮を支えるため不可欠なスキル群を、
それぞれ体系立てて掘り下げる形で学んでいただけます。
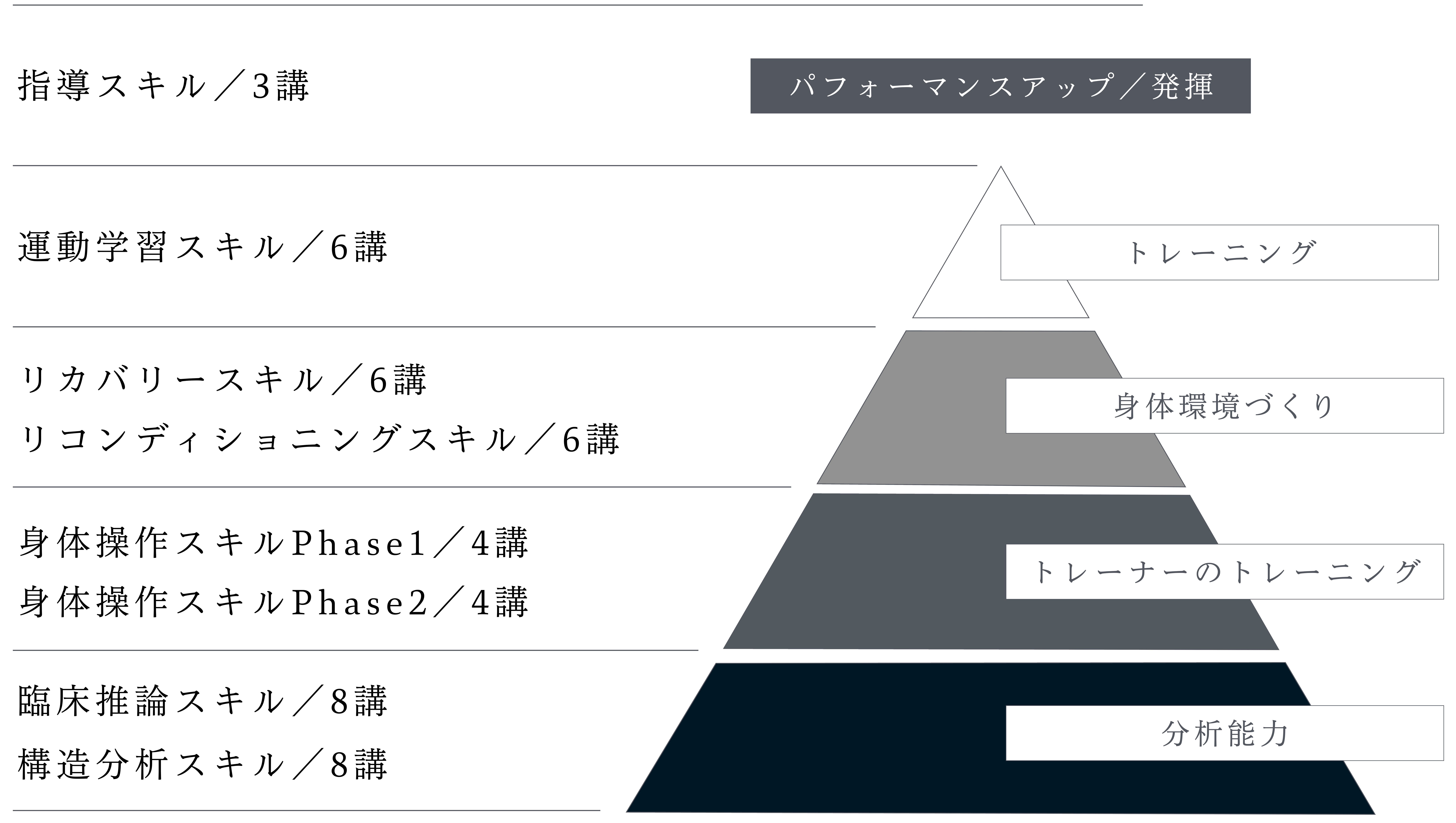
カリキュラム
15ヶ月でコンプリート|7科目で合計45講義
■1ヶ月ごとに3種類の講義を配信(各講義は約1時間)
■配信された講義は在学中は繰り返し視聴可能
■認定スポーツトレーナーコースとは基本的に重複しません(本質部分は重複あり)
相互作用があることで理解や習得レベルがより向上します
- 講義概要/指導スキル(3講)中野 崇
-
トレーナーにとって、選手との間に生まれる信頼関係の有無は、持てる技術や知識をパフォーマンスへと繋げるために不可欠なものです。
自らの振る舞い・言葉を含め選手を取り囲む環境がどのように選手のパフォーマンス発揮に影響を与えるかを理解し、自己と周囲への働きかけを調整しなければなりません。
また、”その場の雰囲気を感じ取り必要に応じて雰囲気を変える” 、あるいは、”選手やチームの変化を予測して備える”など、可能な範囲でそれらを”勝利に適した状態”にまで構築できることが必要です。
本講義では、選手から信頼を得るために必要なこと、選手のパフォーマンスを引き出すために必要な振る舞いを中心に学んでいただきます。指導ノウハウに留まらず、そのやり方の根底にある在り方について自身で整理することができれば同じトレーニングやメッセージであっても伝わり方が変わっていきます。
▽講義ラインナップ
①指導の構造
②自得/振る舞いについての解像度
③場に対する解像度
- 講義概要/運動学習スキル(6講)伊東 尚孝
-
パフォーマンス向上の背景には、環境との相互作用の中で育まれる「運動学習」という極めて重要なメカニズムが存在しています。
運動学習理論には、大きく分けて従来の情報処理モデルに基づいた線形的アプローチと、個体と環境の相互作用を重視する非線形的アプローチ(エコロジカル・アプローチ)が存在します。
線形的アプローチでは、運動を「入力―処理―出力」の系列として捉え、段階的・反復的な練習による技能の定着を目指します。一方、非線形的アプローチでは、環境と身体のダイナミクスが運動パターンを形成するという前提に立ち、状況依存的かつ柔軟な運動制御を重視します。これにより、同一課題に対しても多様な解決戦略が許容され、適応的行動の獲得が可能となります。それゆえ非線形的アプローチの理解は、単なる技術習得だけでなく、長期的なパフォーマンスの発展や再学習にも直結する極めて重要な基盤となります。
本講義では、特に生態心理学を基盤とする非線形の学習理論に焦点を当て、運動課題の設計、変数操作、アフォーダンスの理解、変動性を含む練習の重要性など、多角的な視点からトレーニング現場への導入手法の最適化を検討していきます。
▽講義ラインナップ
①トレーナーが運動学習を学ぶ意義|概論/生態心理学/動的システム理論
②エコロジカル・アプローチ|アフォーダンス/自己組織化/反復
③制約主導アプローチ|5つのプリンシプル/制約操作
④トレーニングへの導入|応用/道具の使用/環境設定
⑤ルーティンセット|JARTAトレーニング4原則における運動学習の原則
⑥競技別の運動学習モデル
- 講義概要/リカバリースキル(6講)赤山 僚輔
-
リカバリースキルは、現場で選手に帯同し、疲労の早期回復や試合に向けたコンディショニングを支えるうえで、極めて重要な役割を果たします。
本講義では、回復の鍵となる「自律神経」「循環」「経絡」などの生理的観点に加え、「心と身体のつながり(心身未分)」といった包括的な視点からリカバリーを捉え、パフォーマンス向上へと直結するリカバリープログラムの構築方法を学びます。
また、リカバリーに関わるトレーナー自身が、まず自らの回復力・調整力を高めることも大切です。
本講義は、現場帯同をされているトレーナーにとって、実践的かつ成長の大きなきっかけとなる内容です。
▽講義ラインナップ
①JARTAリカバリースキル概論
②筋肉骨格系におけるリカバリースキル
③自律神経系におけるリカバリースキル
④循環的観点におけるリカバリースキルの捉え方
⑤循環的観点におけるリカバリースキル実践
⑥経絡・心身未分領域におけるリカバリースキル
- 講義概要/リコンディショニングスキル(6講)鎌田 利武
-
慢性的な炎症や疲労感がなかなか抜けず、コンディションが万全にならない——
こうした状態は局所的な問題ではなく、身体全体のバランスや回復システムの乱れが関係していることが少なくありません。
本講義では、そうした慢性炎症や慢性疲労が繰り返される背景にある複合的な要因である循環障害やリカバリー機能障害、自律神経トラブルなどを整理し、多角的な視点から読み解いていきます。構造的・生理的な視点だけでなく、東洋医学的な観点も交えながら、コンディション不良を引き起こす根本原因に迫ります。
単に知識を得るだけでなく、選手自身が自分自身の身体を知るという意味も含めて、全身の状態を整えるための実践的なリコンディショニング手法を習得することを目的としています。
「なんとなく調子が悪い」「すぐに疲れが戻る」といった選手の声に、より精度の高い対応ができるようになるための引き出しを増やしていきます。
▽講義ラインナップ
①リコンディショニングスキル総論
②セルフコンディショニングの考え方と実践
③東洋医学におけるリコンディショニング
④呼吸と循環 ⑤食養生 ⑥心身のつながりについて
- 講義概要/身体操作スキルPhase1/2(8講)萩 潤也
-
選手やチームのパフォーマンスをアップさせるためには、トレーナー自身が身体操作スキルを向上していくことが不可欠です。
身体操作スキルとは「動きの質を決める能力」であり、広義の意味でトレーナー自身が関わる全ての行為の質を決めることになるからです。
このカリキュラムでは身体操作スキルを向上させるための様々な要素を実践形式で行っていきます。
PHASE1では全身の基盤作りです。単調に感じることもありますが、基本無くして応用なし。
人間に備わっている運動能力を発揮するための超重要フェーズです。
PHASE2の目的は多様性のある身体作り。
特にスポーツで求められるような身体操作スキルに着目した応用編となっています。
▽講義ラインナップ
Phase1
①IAP Control
②Lower Body|image/flexibility/activation
③Upper Body|image/flexibility/activation
④Kinetic Chain
Phase2
①Animal Movement
②Plyometrics/Explosive
③RSSC
④Ex Coordination|バランスボール、棒、etc…
- 講義概要/臨床推論スキル(8講)平山 鷹也
-
臨床推論とは、問題を見つけてから解決するまでの「考えるプロセス」のことであり、トレーナーとして痛みや不調を解決するだけでなく、パフォーマンスアップの観点からも非常に重要なスキルです。
痛みがあるから硬いところをほぐすだけでは、本質的な解決には向かいません。
それどころか対症療法を繰り返し、問題点から目をそらし、長期的に悪化する方向へ進んでしまうことも少なくありません。
なぜその部位は硬くなったのか、なぜそこに痛みが出たのか。
メカニカルストレスや筋・関節的な西洋的視点を深めつつ、経絡や陰陽五行論を基盤にして食事や感情、思想と身体とのつながりを考えるための東洋的視点を統合させて臨床推論の解釈を拡げていく具体的な思考プロセスを共有します。
この講義では様々な現象を解釈するフィルターをアップデートし、これまで身につけてきた知識をさらに深く活用することが可能となります。
▽講義ラインナップ
①局所の臨床推論|当該部位を深くみる
②局所と全体の統合|西洋医学的観点で整理
③OMSSとの統合|経絡
④五行と統合する|五志や五味とも合わせて生活習慣や感情とつなげていく
⑤オンラインでの臨床推論
⑥トレーニングプログラム構築における臨床推論|上肢
⑦トレーニングプログラム構築における臨床推論|下肢
⑧オンラインでのトレーニングメニュー構築における臨床推論
- 講義概要/構造分析スキル(8講)中野 崇
-
トレーナーにとって、選手の動作を精緻に見抜く分析能力は不可欠であり、その精度がトレーニング選択の妥当性や成果の質に決定的な差をもたらします。
その基盤となるのが構造分析スキルです。
あらゆる現象や動作には、それを成立させる基盤としての「構造」が存在します。
この構造を読み解く能力を身につけることで、動作分析の際に本質的な要因と表層的な要素を峻別し、トレーニングや施術において「何が必要で、何が不要か」を論理的・体系的に判断できるようになります。
さらに、本講義では構造のモデリング技術も扱います。
構造化におけるモデリングとは、事象を構成する要素とそれらの相互関係を抽出・図式化する技法であり、これを習得することで、複雑な運動現象や指導課題に対しても、要素間の因果構造を明確に捉えることが可能になります。
これにより、より汎用的で再現性の高い解決策を導き出すスキルが培われます。
講義内では「競技構造」「動作構造」「トレーニング構造」の3つを中心に、それぞれに適したモデリングパターンを体系的に学習します。
これらは一過性のテクニックではなく、トレーナーとしての活動を通じて長期的かつ汎用的に活用できる、極めて実用性の高い分析フレームです。
▽講義ラインナップ
①構造分析がなぜ必要か|モデリング・現象の構造化
②やるべきこと方程式と分析力向上の3識
③競技構造と単純動作の分析
④エネルギーリターンの構造
⑤競技動作の構造1|移動系(動き出し;盗塁、陸上)
⑥競技動作の構造2|スイング系(ゴルフ/テニスフォアH/卓球)
⑦概念の構造分析
⑧観察力の構造








